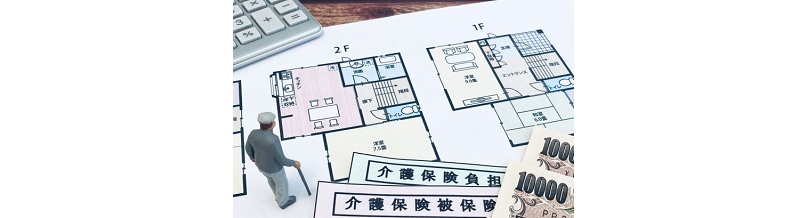高齢者の引越しは、体力的・精神的な負担に加え、介護や医療の継続性、住環境の整備など多くの配慮が必要です。
ここでは、高齢者の引越しにおけるポイントを「事前準備」→「引越し当日」→「引越し後」の流れで詳しく解説します。

目次
高齢者の特性に配慮した計画づくり
高齢者の引越しには、若年層の引越しとは異なる身体的・精神的・環境的な特性への配慮が必要です。
特に、事前計画がその後の生活の安定や本人の安心感に大きく影響します。
【1】なぜ「計画づくり」が重要か?
■ 高齢者特有のリスク
- 体力・筋力の低下:重い荷物の移動が難しく、ちょっとした段差でも転倒リスクあり。
- 環境の変化に対する不安・ストレス:認知症や加齢により、生活の変化を受け入れるのに時間がかかる。
- 医療・介護の中断リスク:既存の支援が途切れると、生活や健康状態に悪影響を及ぼす可能性あり。
■ 無計画な引越しの影響
- 精神的混乱や身体の不調の悪化
- 転倒・事故などの安全面のトラブル
- 医療・介護支援が受けられなくなる事態
そのため、引越しそのものよりも「その前の準備」が最も重要だと言えます。
【2】本人の状態と希望を最優先に考える
■ 健康状態・要介護度の把握
- ケアマネジャーや主治医と連携して、身体能力・認知機能・生活習慣を確認。
- 要支援・要介護認定を受けている場合、サービスの継続計画が必須。
■ 本人の意思と気持ちの尊重
- 「どこに引っ越すのか」「誰と住むのか」「なぜ引越すのか」を丁寧に説明。
- 急に決めてしまうと強い不安や抵抗を生むことがあるため、事前に何度も話し合いを。
【3】引越し先の環境と立地の確認ポイント
■ バリアフリー設計がされているか
- 段差がない構造(スロープ、手すり)
- トイレ・風呂の動線が安全か
- エレベーターの有無(集合住宅の場合)
■ 医療・介護施設へのアクセス
- 徒歩または公共交通機関で通いやすいか
- 緊急時に対応できる病院が近くにあるか
■ 地域環境の安全性と利便性
- スーパーやドラッグストアが近くにあるか
- 治安・騒音・交通量など、安心して暮らせるか
【4】移動・作業負担を軽減する引越し計画
■ 荷造り・整理は早めに、少しずつ
- 一度にやらず、毎日30分など小分けに作業を進める。
- 思い出の品や写真アルバムなどは、ゆっくり一緒に見ながら整理するのが理想。
■ 家族または専門業者のサポートを活用
- 専門の福祉対応引越しサービス(シニア引越し専門業者)を検討。
- 本人は無理に作業せず、計画管理と確認役に回ってもらうと安心感が高まる。
【5】医療・介護サービスの継続に向けた調整
■ 引越し前にやるべき対応
- 担当ケアマネジャーとの打ち合わせ(新しい地域への引き継ぎ)
- 医療機関の紹介状・薬の確保(1週間~10日分多めに処方)
■ 介護保険の対応
- 市区町村をまたぐ場合:介護保険証の返納 → 転入先で再申請。
- サービス提供事業者の変更が必要になるケースもある。
【6】計画書を作成して「見える化」する
■ おすすめの項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 引越しの目的・理由 | 例:家族の近くで生活するため |
| 引越し日・業者名 | 事前に日程を本人にも周知 |
| 荷造り計画 | どの部屋をいつ片付けるか |
| 医療・介護調整 | ケアマネ連携日、病院連絡日など |
| 引越し先情報 | 間取り、設備、立地の確認チェック |
高齢者の引越し計画は「準備8割・当日2割」
高齢者の引越しは、「本人の心身の状態」と「移動後の生活の安定性」を両立させることが大切です。
最も重要なのは、本人の気持ちに寄り添いながら、周囲がしっかりとサポート体制を築くこと。
無理のないスケジュールと、綿密な準備によって、安心して新生活に移行することが可能になります。

安全・安心な移動を優先
高齢者にとって、引越しそのものが身体的な負担だけでなく、精神的な不安・混乱を伴う一大イベントです。
とくに移動当日は、環境が大きく変化するタイミングであり、本人や家族にとって注意すべき点が多く存在します。
【1】高齢者の引越しに特化した業者を選ぶ
■ 専門業者の特徴
- 福祉対応・高齢者専門サービスを提供する引越し業者の利用がおすすめ。
- 介護資格保有スタッフによる対応や、家具配置・荷解きまで含めた「手ぶら引越しプラン」などがある。
■ サービス例
| サービス内容 | 配慮ポイント |
|---|---|
| 家具・家電の再設置 | バリアフリー配置、動線確認 |
| 段差への仮設スロープ設置 | 車椅子・歩行補助具使用者向け |
| 安全確認スタッフの同行 | 転倒防止・緊急時対応 |
■ 家族が業者に伝えるべきこと
- 本人の身体状況(歩行、排泄、認知症の有無)
- 当日の同伴者の有無
- 特に壊れやすい・大切な荷物の情報
【2】本人の体調・心理状態への配慮
■ 事前の健康管理
- 数日前から本人の体調(睡眠・食欲・便通など)をよく観察。
- 主治医の許可を得て、念のための処方薬を余分に用意(酔い止め・鎮静剤なども含む)。
■ 精神的ケアのための工夫
- 引越しの目的や行き先を繰り返し丁寧に説明(認知症のある方には特に重要)。
- 移動中も「安心して大丈夫」「もうすぐ新しいお部屋だよ」などの声かけを継続。
【3】当日の動線と安全確保
■ 住宅内での対策
- 廊下・玄関に物を置かない:つまずき防止。
- スリッパではなく滑りにくい靴やリハビリ用シューズを使用。
- トイレ・洗面所がすぐ使える状態にする:水分摂取や服薬の直後に備えて。
■ 搬出・搬入の際の注意
- 高齢者本人は作業場所から離れた場所で待機(ホコリ・騒音の影響を避ける)。
- 家族が1人は常に付き添い、安全確認と誘導を行う。
- 引越し前に新居の動線チェック:仮設の手すり・スロープの設置も検討。
【4】移動手段と時間の工夫
■ 安全な移動方法の選択
| 移動手段 | 向いているケース |
|---|---|
| 介護タクシー | 車椅子・寝たきりの方、病院同伴が必要な方 |
| 家族の車 | 比較的元気な高齢者で距離が短い場合 |
| 民間福祉移送サービス | 長距離や公共交通機関を使えない方 |
■ 時間帯とスケジュール調整
- 午前中(9時〜11時)に移動開始が理想:体力のある時間帯。
- 引越しは「半日で終わる」スケジュールを前提にし、午後は休息に充てる。
【5】引越し後すぐに整えるべきもの
■ 当日中に用意しておきたい環境
- ベッド・布団・トイレ・お茶・常備薬・着替えなど、「すぐ使うセット」をあらかじめまとめておく。
- 電気・ガス・水道の開通を事前に済ませておく。
- 「ここがあなたのお部屋」「いつもと同じ食器や毛布だよ」と説明しながら安心感を与える。
【6】緊急時への備え
■ 移動中の異変に備える
- 吐き気、ふらつき、発熱、混乱などがあれば無理をせず中断。
- 移動用の応急セット(水分、常備薬、紙おむつ、着替え、保険証のコピーなど)を持参。
■ 緊急連絡体制を確認
- 家族同士、業者、医療機関との連絡がすぐ取れるようにスマホ・連絡先を準備。
- ケアマネジャーや医療機関に**「当日、体調悪化した場合の相談窓口」**を確認しておく。
移動の安全確保こそが、引越し成功の鍵
高齢者の引越しでは、「安全な移動」「安心できる環境」が最優先です。特に移動日当日は、無理をせず、本人の体調と心理状態に合わせて丁寧に進めることが、トラブルや体調悪化を未然に防ぐ大きなポイントとなります。

生活再建と環境調整
高齢者の引越しは、終わってからが本当のスタートです。
新しい環境に適応し、健康を保ちながら穏やかに生活を送るためには、生活リズムの再構築・住環境の調整・医療や介護の継続体制整備・心理的ケアが不可欠です。
【1】生活リズムの再構築:日常生活の安定が最優先
■ 生活時間を整える
- 起床・食事・服薬・排泄・入浴のタイミングをなるべく引越し前と同じにする。
- 食事の用意が難しい場合は、宅配弁当(高齢者向け)や見守り配達サービスの利用も有効。
■ 家事・身の回りのサポート
- 洗濯・掃除・ごみ出しなどに不安がある場合は、訪問介護(生活援助)を早期に導入。
- 家族がすぐ対応できない場合は、家事代行サービスや地域包括支援センターに相談。
【2】住環境の安全性と使いやすさを確認・調整
■ バリアフリー点検(引越し後すぐ行うべき)
| チェック項目 | 対応策 |
|---|---|
| 床に段差・滑りやすい場所がある | スロープ・滑り止めマット設置 |
| 夜間の移動時に暗い場所がある | 足元灯・センサーライトの設置 |
| トイレや浴室に手すりがない | 後付け手すりの導入(介護保険で補助あり) |
| ベッドが高すぎる・低すぎる | 高さ調整・介護ベッドへの変更 |
■ 配置の工夫
- リモコン・電話・薬・眼鏡などは「本人が手を伸ばせる位置」に統一。
- 家具はなるべく少なく、動線を広く取っておく(車椅子・歩行器対応も考慮)。
【3】医療・介護サービスの再開と引き継ぎ
■ 介護保険サービスの調整
- 市区町村が変わった場合は、介護保険被保険者証の返納→再発行が必要。
- 引越し先のケアマネジャー選定 → ケアプラン作成 → サービス提供開始という流れ。
■ 医療機関との連携
- 主治医の変更がある場合は、紹介状・検査データ・服薬情報を持参して診療継続へ。
- 定期通院が必要な場合は、移動手段(家族・介護タクシーなど)の確保も同時に計画。
■ 訪問診療・訪問看護の導入
- 通院が困難な場合は、訪問医・訪問看護師の体制を地域包括支援センターに相談。
【4】心理的なケアと「居場所づくり」
■ 慣れない環境への不安を和らげる
- 引越し前から使っていた家具・道具・カレンダーなどを配置し、見慣れた空間を作る。
- 「ここがあなたのお部屋だよ」「今まで通り暮らせるからね」と言葉での安心感の提供。
■ 認知症がある場合の工夫
- 同じ行動を何度も繰り返す・混乱が見られる場合も、焦らず穏やかに対応。
- デイサービスの早期利用を進めると、「新しい生活の中の居場所」になりやすい。
■ 地域とのつながりをつくる
- 地域包括支援センター主催のサロン・体操教室・認知症カフェなどに参加。
- 近隣とのあいさつや軽い会話を通じて、孤立予防と生活意欲の維持を図る。
【5】家族の役割と定期的な見守り体制
■ 家族のサポートでできること
- 最初の数週間は頻繁に訪問し、変化や不安のサイン(食欲減退・無言・不機嫌など)を見逃さない。
- 「気にかけてもらっている」という実感が、精神的な安定につながる。
■ 緊急時への備え
- 救急対応マニュアル、かかりつけ医の電話番号、服薬情報、緊急連絡先を一覧にして掲示しておく。
- 緊急通報装置(ペンダント型など)や見守りセンサーの導入も検討。
生活再建と環境調整は「段階的」に、「本人主体」で
引越し後の生活を成功させるには、新しい環境を「本人にとっての安心できる居場所」に変えていくことが最優先です。
リズム・環境・ケア体制の3本柱を段階的に整えながら、家族や支援機関が一体となって見守ることが、スムーズな生活再建のカギになります。

家族側のサポートと注意点
高齢者の引越しは、本人だけで完結するものではありません。家族が主体的に関わることで、安全で負担の少ない引越しが可能になります。
ここでは、家族が担うべきサポートの具体的な内容と、注意すべき点を段階ごとに詳しく説明します。
【1】引越し前:家族が果たすべき役割
■ 本人への理解と説明
- 引越しの理由や目的を繰り返し丁寧に伝える(特に認知症のある方)。
- 例:「病院に近いおうちに行くんだよ」「安全に暮らせるようにするんだよ」など、本人の安心感を優先した説明。
- 「一緒に決めている」という姿勢を持つことで、拒否反応を和らげる。
■ 準備作業の実行・管理
- 荷物の仕分け・不要物の処分・書類の整理を家族が主体で段取り。
- 大切な思い出の品は必ず本人に確認を取りながら対応。
- 引越し業者との打ち合わせ、ケアマネ・医療機関への連絡も家族が担当。
【2】引越し当日:同行と現場サポート
■ 本人への付き添いが基本
- 本人の体調、精神状態を観察しながら、付き添って行動を誘導・支援。
- 「荷物をまとめる」「急いで移動する」など、焦りを見せないようにする。
■ 現場での確認ポイント
| 内容 | 家族がすべきこと |
|---|---|
| 家具・家電の配置 | 動線を確認し、バリアにならない配置を指示 |
| 電気・水道・ガスの立ち会い | 開通確認とその場での使い方説明 |
| 寝具・トイレの位置確認 | 当日から使えるよう設置を最優先 |
【3】引越し後:生活の立ち上げを支援する
■ 安心できる環境の構築
- 旧居と同じような配置・持ち物を優先し、「見慣れた空間」の再現を意識。
- 最初の1週間はできるだけ頻繁に顔を出す・電話をすることで不安軽減。
■ 医療・介護体制の再構築サポート
- 地域包括支援センターやケアマネとの連絡窓口を家族が担い、サービスの立ち上げを支援。
- 主治医の切り替え・薬局の手続き・通院送迎の段取りも忘れずに。
■ 心の変化に注意
- 引越し後の高齢者は**「うつ状態」「無気力」になりやすいため、表情・食欲・口数をよく観察**。
- 「大丈夫?」より「これ、美味しいから食べてみようよ」など、自然なコミュニケーションが効果的。
【4】注意すべきポイント
■ 本人の自尊心を傷つけない対応
- 物の処分や環境変更は「勝手に決める」のではなく「相談しながら進める」ことが重要。
- 「もう年だから無理だよね」などの言葉は避け、できることにはなるべく本人に参加してもらう。
■ 認知症のある場合の特別な配慮
- 環境が変わることで混乱や妄想が強まるケースあり。
- 本人の理解力に合わせて情報量を調整し、同じ説明を何度でも繰り返す覚悟が必要。
■ 家族の負担にも限界がある
- サポートにかかる時間・労力が大きいため、訪問介護・家事代行・見守りサービスなどの外部リソースを活用。
- 家族が「抱え込まない」姿勢を持つことも、長期的には本人のためになる。
【5】家族が事前に準備しておきたい情報・書類一覧
| 書類・情報 | 用途 |
|---|---|
| 介護保険証 | サービス開始・申請に必要 |
| 健康保険証・お薬手帳 | 医療機関受診時に必要 |
| 主治医の紹介状 | 医師変更時に持参 |
| 緊急連絡先一覧 | 万一の際にすぐ対応できるよう掲示 |
| 金融・保険情報 | 支払い・引き落とし手続きに必要 |
家族のサポートは「段取り」と「寄り添い」の両立がカギ
高齢者の引越しでは、家族が段取り役・調整役として実務を支えながら、本人の気持ちに寄り添うコミュニケーションをとることが最も重要です。
引越しを単なる「作業」にしないよう、本人の安心と尊厳を守りながら、一歩ずつ新しい生活へ導いていきましょう。

高齢者の引越しは「生活の継続性」と「安心の確保」が最優先
高齢者にとっての引越しは、単なる「住まいの移動」ではなく、生活の再設計であり、心身への大きな負担を伴います。
そのため、「安全に、安心して、これまで通りの生活が続けられる」ことを最優先に考えた引越し計画が必要です。以下に、重要なポイントをまとめます。
【1】「生活の継続性」が最も重要な理由
- 高齢者は環境の変化に弱く、日常のルーティンが崩れると体調や認知機能が悪化することがあります。
- 引越し後も「これまで通りの生活」ができるよう、生活リズム・医療・介護・人間関係の継続が求められます。
【2】「安心の確保」のために必要な配慮
■ 心の安心
- 慣れ親しんだ家具・持ち物をできるだけ持ち込み、「自分の空間」だと感じられる工夫をする。
- 家族やケアスタッフがこまめに声をかけ、孤独感・不安感を軽減。
■ 身体の安心
- バリアフリー対応、動線確保、段差解消、手すり設置などの安全な住環境整備。
- 医療・介護体制を事前に確認し、引越し後すぐにサービスが利用できるように調整。
【3】引越し前・当日・後のポイント
| フェーズ | 優先すること |
|---|---|
| 引越し前 | 健康状態と要介護度の確認、本人の意思尊重、医療・介護サービスの引き継ぎ |
| 引越し当日 | 安全な移動、家族の付き添い、生活必需品のすぐ使える配置 |
| 引越し後 | 生活リズムの再構築、住環境の調整、医療・介護サービスの継続、心理的フォロー |
【4】家族が果たすべき役割
- 本人の不安を和らげる丁寧な説明と共感。
- 荷造り・手続き・段取りを実務的にサポート。
- 引越し後も数週間は頻繁に訪問・連絡を行い、見守り体制を維持。
【5】引越しは「再出発」ではなく「日常の延長」
- 高齢者にとっては、変化の少ない、落ち着いた暮らしの継続が何よりも安心につながります。
- 引越しは新しい暮らしを「ゼロから始める」のではなく、今までの生活を新しい場所に「そのまま運ぶ」ように設計することが大切です。
結論:
高齢者の引越しでは、「生活の継続性」と「安心の確保」が何よりも優先されるべきです。
「体調・気持ち・介護・医療・人とのつながり」これらが引越しを機に途切れないように支えることが、ご本人の安定と幸せに直結します。

異なる事情・ニーズ【関連ページ】
- 一般的な引越しと異なる事情・ニーズ
- 単身赴任・一人暮らし向け引越しガイド
- 家族・子連れの引越し完全マニュアル
- カップル・同棲開始引越しガイド
- 高齢者・介護を伴う引越し
- 離婚・別居に伴う引越し
- 転職・異動を伴う引越し
- 単身引越しの賢い方法
- 長距離引越しを賢く行う方法
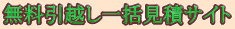
・ズバット引越し比較 ![]() 当サイトNo1利用率
当サイトNo1利用率
大手から中小まで全国220社以上の業者と提携しており最短1分で一番安い業者が探せる優良一括見積サイト。
・引越し侍![]()
CMでおなじみの引越し一括見積りサイトです。全国352社の業者と提携しており5,068万件という紹介をしています。
・引越し価格ガイド![]()
利用者の95.2%がまた利用したいという一括見積サイト
・引越しラクっとNAVI![]()
ビデオ通話によるオンライン見積もりも。専用のサポートセンターが1度ヒアリングをすることで、引越し会社と話すことなく見積りが出てきます。