引越しに関して利用できる補助金・助成金制度が、国・自治体・一部企業などから提供されている場合があります。

国の支援制度
引越しに直接使える国の制度は数は多くありませんが、「住宅取得」「子育て」「地方移住」などのライフイベントと連動した支援制度を活用することで、引越し費用や住居関連の負担を大きく減らすことが可能です。
■ 1. 結婚新生活支援事業(内閣府)
◆ 概要:
新婚世帯が「新生活」をスタートする際の【住宅取得費】【引越し費用】を国が一部補助する制度。補助は市区町村を通じて行われます。
◆ 主な条件:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 婚姻日の時点で夫婦ともに39歳以下(※自治体により34歳以下の場合も) |
| 所得要件 | 世帯所得500万円未満(=年収で約600万円未満) |
| 対象費用 | 引越し費用、敷金・礼金、仲介手数料、住宅取得費用など |
| 補助金額(上限) | 最大60万円(重点支援地域)/最大30万円(通常地域) |
| 必要書類例 | 婚姻届受理証明書、収入証明書、賃貸契約書または登記簿など |
◆ 注意点:
- 自治体によって採択の有無が異なるため、対象エリアの確認が必須
- 申請期間も自治体ごとに異なる(例:4月~翌2月末など)
◆ 情報源:
- 内閣府 結婚新生活支援事業ページ
■ 2. 住居確保給付金(厚生労働省)
◆ 概要:
仕事を失った/収入が減少した人に対し、賃貸住宅の家賃を国が一定期間補助してくれる制度。
◆ 主な条件:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 離職・廃業後2年以内、または就労時間が減り収入減少した人 |
| 家賃補助額 | 市区町村が定める住宅扶助基準額の範囲内(例:東京23区=53,700円) |
| 補助期間 | 原則3か月(条件により最長9か月) |
| 条件 | ハローワークでの就労支援への参加義務あり |
◆ 注意点:
- 家賃補助であり、引越し費用そのものの補助ではないが、新生活立て直し時に活用可
- 原則として現在の賃貸に住み続ける人向けだが、転居後でも申請可能な場合あり(要確認)
◆ 情報源:
- 厚生労働省|住居確保給付金
■ 3. 地方創生移住支援金(総務省)
◆ 概要:
東京都23区に住んでいる、または通勤していた人が地方へ移住し、就業・起業する場合に支給される支援金制度。
◆ 主な条件:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 東京23区在住者、または23区に通勤していた者(通算5年以上) |
| 対象地域 | 各都道府県が指定する地方自治体(例:長野県、福井県、高知県など) |
| 支援金額 | 単身者:60万円/世帯:100万円+子ども1人につき最大30万円加算 |
| 活用条件 | 地方自治体が指定する企業への就職/地域課題解決型起業/テレワークなど |
◆ 注意点:
- 引越し費用そのものの補助ではないが、移住に伴う大きな資金として活用可能
- 子育て世帯への優遇がある
◆ 情報源:
- 地方創生テレワーク・移住支援金サイト
■ 4. すまい給付金(※2021年度で終了・今後の再開に注意)
◆ 概要(旧制度):
住宅購入者に対して最大50万円を給付していた制度。現在は終了していますが、今後の住宅政策の中で復活の可能性もあるため動向注視が必要です。
【まとめ:国の制度の使い分け】
| 対象者・状況 | おすすめの制度 |
|---|---|
| 新婚夫婦 | 結婚新生活支援事業 |
| 離職・休業などで家計困窮 | 住居確保給付金 |
| 地方へ移住・就職/起業 | 地方創生移住支援金 |
| 将来住宅購入を予定 | ※今後の住宅支援政策(すまい給付金の再開など) |

自治体の支援制度
自治体独自の補助金・助成金制度は、居住促進・少子化対策・地域活性化などの目的で設けられており、引越し費用や家賃補助、住居取得などに対する支援が中心です。
内容は自治体ごとに異なるため、ここでは代表的な制度のパターンと具体例を示します。
【1】引越し費用の補助
◆ 概要:
親世帯との「同居・近居」を促進する目的や、人口減少対策の一環として、引越し費用そのものに補助を出す自治体があります。
◆ 代表例:東京都新宿区「多世代近居・同居促進助成」
- 【補助額】
・最大20万円(複数世帯)/最大10万円(単身世帯) - 【条件】
・親世帯と1km以内の距離に引越す
・新宿区内に住民票を移すこと - 【対象経費】
・引越し費用、仲介手数料、敷金・礼金など
【2】家賃補助・住宅支援金
◆ 概要:
特に子育て世帯や若年夫婦などを対象に、月額の家賃を補助する支援制度があります。
◆ 代表例:東京都新宿区「子育てファミリー世帯家賃助成」
- 【補助額】
・月3万円×最長3年(最大108万円) - 【条件】
・中学生以下の子どもがいる
・一定の所得制限あり
・新宿区への転入・転居が対象
【3】住宅取得費用の補助(定住促進)
◆ 概要:
地方移住者、子育て世帯、若者向けに、住宅購入費の一部やリフォーム費用を支援。
◆ 代表例:長野県飯田市「定住促進住宅取得奨励金」
- 【補助額】
・最大100万円(新築)+子ども加算あり - 【条件】
・市外からの転入
・居住継続義務あり(例:10年以上定住)
【4】若者・子育て世帯の移住支援金(地方移住)
◆ 概要:
地方移住者に対して、国の支援金(移住支援金)と連動して、自治体独自の加算支援を用意しているケースもあります。
◆ 代表例:山形県庄内町「UIターン者定住支援金」
- 【支給額】
・国の制度に加え町から最大20万円加算 - 【条件】
・町内での就職・定住が必要
【5】新婚・子育て支援型住宅助成
◆ 概要:
結婚・出産を契機に引越しする世帯に対して、住宅関連費用(引越し含む)を支援。
◆ 代表例:埼玉県加須市「結婚新生活支援事業」
- 【補助額】
・最大30万円(世帯収入に応じて変動) - 【条件】
・婚姻後1年以内の世帯
・市内で新たに住居取得または賃貸契約を行うこと
■ 支援を受けるためのチェックポイント
| チェック項目 | 解説 |
|---|---|
| 支援対象エリアか | 市区町村ごとに制度の有無が異なる(同じ都道府県内でも異なる) |
| 世帯条件 | 「若者世帯」「新婚」「子育て」「Uターン」「多世代」など、条件に合致しているか |
| 所得制限の有無 | 一定の年収・所得制限が課されることが多い |
| 引越し先での住民票移動 | 「転入完了」が支給条件になるケースが多い |
| 事前申請の有無 | 一部制度は「引越し前の申請」が必須。事後申請不可の場合に注意 |
■ 情報収集のコツ
- 自治体名+「引越し 補助金」「住まい 支援」などで検索
- 市区町村の公式サイトの「住まい」「定住促進」ページを確認
- 「移住ポータルサイト」や都道府県の定住相談窓口も活用
■ まとめ:制度ごとの違い比較
| 制度タイプ | 内容 | 主な対象者 | 支給額の目安 |
|---|---|---|---|
| 引越し費用補助 | 実際の引越し代に対する補助 | 多世代・移住者など | ~20万円程度 |
| 家賃補助 | 毎月の家賃を一部支給 | 子育て・若者夫婦など | 月1~3万円×数年 |
| 住宅購入・改修費補助 | 家の購入やリフォーム費用への補助 | 地方移住・若年層など | ~100万円以上 |
| 新婚生活支援 | 結婚に伴う住居取得・引越し費用への補助 | 新婚夫婦 | 最大30~60万円 |
| 地方移住支援金 | 国制度+自治体加算で支援 | 東京圏からの移住者 | 最大100万円以上 |

その他の支援制度
「国の制度」や「自治体独自の補助金・助成金」以外に活用可能な、公的・半公的機関・民間との連携による支援制度を紹介します。経済的な事情やライフイベントに応じて使える制度が複数あります。
■ 1. 住居確保給付金(厚生労働省)※再掲(重要)
◆ 概要:
失業や収入減少で住まいを失う恐れがある方を対象に、一定期間、家賃相当額を国が補助してくれる制度です。生活困窮者自立支援制度の一部です。
◆ 詳細:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支援対象 | 離職・廃業後2年以内、または休業・収入減による生活困窮 |
| 支援内容 | 家賃相当額(月5~7万円程度)を原則3ヶ月(最大9ヶ月)支給 |
| 支給方法 | 家主に直接振込(自己受取不可) |
| 必須条件 | ハローワークでの求職活動・生活支援相談等を継続 |
◆ 活用タイミング:
- 離職直後の引越しや、家賃滞納のリスクがある際に非常に有効
■ 2. 緊急小口資金・総合支援資金(社会福祉協議会)
◆ 概要:
失業・減収など緊急時の生活資金を、無利子・保証人なしで貸し付ける制度(最大80万円超)。
◆ 詳細:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支援内容(例) | ・緊急小口資金:最大10万円 ・総合支援資金:最大60万円超 |
| 利子・保証人 | 無利子・無担保 |
| 返済猶予・免除規定 | 条件によっては返済免除措置もある(生活保護転換など) |
| 申請先 | 市区町村の社会福祉協議会 |
◆ 活用タイミング:
- 引越し資金を一時的にまかなう必要がある場合
- フリーランス・個人事業主の収入減などにも対応
■ 3. 母子・父子家庭(ひとり親)支援
◆ 概要:
ひとり親世帯に対し、住居の安定を目的に家賃補助や住宅手当、引越し費用の一部助成が行われることがあります。
◆ 支援例(自治体により異なる):
| 支援内容 | 説明 |
|---|---|
| 母子父子寡婦福祉資金貸付金 | 住宅取得・引越し等の資金貸付(最大150万円程度) |
| ひとり親家賃助成 | 月額2~3万円の家賃補助(自治体ごとに実施) |
| 引越し費用補助 | 自治体によっては転居に伴う初期費用を助成 |
◆ 注意点:
- 所得制限あり
- 自治体窓口で個別相談が基本
■ 4. 社宅・官舎・福利厚生による支援(勤務先)
◆ 概要:
公務員や大企業社員などでは、転勤や赴任時の引越し費用・住宅費補助が制度化されています。
◆ 代表的支援内容:
- 引越し費用の全額or一部会社負担
- 社宅・官舎の提供(家賃格安)
- 借り上げ社宅制度(実質家賃補助)
◆ 対象者:
- 国家公務員・地方公務員
- 大手企業・上場企業社員など
◆ 活用ポイント:
- 会社総務・人事部に「転居に関する福利厚生」の確認が必須
- 内定段階で条件を確認できる場合もある
■ 5. 民間団体・NPO・移住支援協議会の支援
◆ 概要:
一部のNPOや地域移住センターでは、移住者や生活困窮者の引越し・住まい支援を行っています。
◆ 代表例:
- 地域おこし協力隊(就職・引越し支援)
- 地方移住推進NPO(住居紹介+助成案内)
- 生活困窮者支援団体(無料引越し支援の事例あり)
■ まとめ:対象別支援制度早見表
| 対象者/状況 | 活用可能な支援制度 |
|---|---|
| 失業・収入減少 | 住居確保給付金、緊急小口資金、総合支援資金 |
| ひとり親家庭 | 母子父子福祉資金、家賃補助制度 |
| 新卒・就職・転職者 | 会社による社宅・引越し費用補助 |
| 移住希望者 | 地方移住支援協議会、NPO連携支援、移住支援金 |
| 公務員・大手企業社員 | 官舎・社宅制度、福利厚生による引越し費用負担 |
| 緊急避難(DVなど) | 自治体や支援団体のシェルター・匿名引越し支援など |
4. 申請手続きと注意点
- 情報収集:引越し先の自治体の公式ウェブサイトや窓口で、利用可能な支援制度を確認しましょう。
- 申請条件の確認:各制度には年齢、所得、家族構成などの条件があります。自身が該当するかを確認してください。
- 必要書類の準備:申請には、住民票、所得証明書、婚姻届受理証明書などが必要となる場合があります。
- 期限の確認:申請期限が設定されている場合が多いため、引越し計画と合わせてスケジュールを立てましょう。
これらの支援制度を活用することで、引越しに伴う費用負担を軽減できます。詳細は各自治体の公式情報を参照し、適切な手続きを行ってください。

申請手続きと注意点
引越しに関わる補助金・助成金・支援制度を利用する際には、正しい申請手順を踏むことと、制度ごとのルールを厳守することが非常に重要です。
ここでは、申請手続きの一般的な流れと、共通・個別の注意点を体系的に解説します。
■ 1. 一般的な申請手続きの流れ(5ステップ)
| ステップ | 内容 | 詳細 |
|---|---|---|
| ① 制度の情報収集 | 自治体・国・会社・NPOなどの公式情報を確認 | 市区町村の「住まい・定住支援」ページや厚労省サイトなど |
| ② 要件の確認 | 年齢、所得、家族構成、住所など | 世帯年収・扶養の有無・住民票の移動有無なども重要 |
| ③ 書類の準備 | 申請書・住民票・収入証明・領収書など | 申請時に不備があると再提出になることも |
| ④ 窓口申請/郵送申請/オンライン申請 | 制度によって形式が異なる | 役所窓口・社協・NPOなど、提出先を事前確認する |
| ⑤ 結果通知・支給 | 書類審査後、支給決定通知→振込など | 審査に1~2ヶ月かかる場合あり。口座確認も必要 |
■ 2. よくある提出書類一覧
| 書類名 | 主な用途 |
|---|---|
| 申請書 | 申請者情報・制度ごとの同意確認など |
| 住民票 | 引越し先住所の証明 |
| 収入証明書(源泉徴収・課税証明) | 所得制限の確認 |
| 引越し業者の領収書 | 実際の引越し費用の証明 |
| 賃貸契約書または登記簿 | 家賃・購入の証明 |
| 婚姻届受理証明書 | 新婚支援制度の場合などに必要 |
| 離職証明書 | 住居確保給付金などで必要 |
■ 3. 制度別の申請窓口と申請方法の違い
| 制度名 | 申請窓口 | 方法 |
|---|---|---|
| 結婚新生活支援事業 | 市区町村役所(住民課など) | 窓口 or 郵送 |
| 住居確保給付金 | 自立相談支援窓口(福祉課) | 窓口申請のみ |
| 緊急小口資金・総合支援資金 | 各市区町村の社協 | 原則:窓口申請 |
| 地方移住支援金 | 都道府県+市町村 | 窓口+事後申請 |
| 住宅取得・改修補助金(自治体) | 住宅政策課・定住支援室等 | 郵送 or 窓口 |
| 民間NPO等の支援制度 | 支援団体の窓口 or 電話 | 対面・電話・Web |
■ 4. 申請に関する注意点(共通)
● ① 事前申請が必要な制度に注意
- 多くの制度は「契約・引越しの前」に申請または予約申請が必要
- 引越し後に申請しても対象外になるケース多数(例:婚姻支援、住宅取得補助など)
● ② 同一内容で複数支援を受けられないことがある
- 引越し費用に関する補助が自治体+国で二重給付不可の場合あり
- 「自治体の移住支援金」+「国の移住支援金」は合算可能だが調整が必要
● ③ 受給後の居住条件に注意
- 「支給後○年以上定住が必要」などの条件あり(違反時は返還対象)
- 子育て支援・定住促進系の補助金に多い
● ④ 引越し業者の領収書は必須かつ形式に注意
- 個人の軽トラ・友人に頼んだ場合は対象外
- 「発行者・宛名・日付・金額」の記載が必要
- 領収書が電子の場合、印刷・署名・捺印が必要な場合もある
■ 5. 不備・失敗しやすいポイント
| よくあるミス | 防止策 |
|---|---|
| 引越し後に制度を知り、申請ができなかった | 情報収集を引越し前に徹底する |
| 書類不備で再提出を求められた | 提出前にチェックリスト確認 |
| 所得制限を見落とし、対象外だった | 申請前に前年所得確認 |
| 同棲や婚姻日が申請条件とずれていた | 日付と住所変更タイミング調整 |
■ 6. 申請サポートを受ける方法
- 役所の「くらし相談窓口」や「定住支援室」:制度紹介+書類記入アドバイスあり
- 社会福祉協議会(社協):困窮者向け支援の申請補助も行う
- 地域包括支援センター(高齢者):介護・福祉・引越しの連携が可能
- 移住支援NPO・相談窓口:地方移住の場合に制度横断でサポート可
■ まとめ:成功するための申請ルール
- 引越し前に必ず確認と事前申請!
- 公式サイトだけでなく役所窓口でも相談する
- 書類・領収書類はすべて控えを取り、保存しておく
- 審査や入金には1〜2ヶ月かかる前提で計画的に動く

引越しの手順【関連ページ】
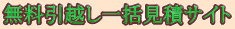
・ズバット引越し比較 ![]() 当サイトNo1利用率
当サイトNo1利用率
大手から中小まで全国220社以上の業者と提携しており最短1分で一番安い業者が探せる優良一括見積サイト。
・引越し侍![]()
CMでおなじみの引越し一括見積りサイトです。全国352社の業者と提携しており5,068万件という紹介をしています。
・引越し価格ガイド![]()
利用者の95.2%がまた利用したいという一括見積サイト
・引越しラクっとNAVI![]()
ビデオ通話によるオンライン見積もりも。専用のサポートセンターが1度ヒアリングをすることで、引越し会社と話すことなく見積りが出てきます。

