家族・子連れでの引越しは、「物理的な荷物の移動」以上に、子どもの心のケア、家族の生活リズム維持、学区変更などの複雑な要素を含みます。
このマニュアルでは、引越しを「準備」→「引越し当日」→「引越し後」→「生活の安定化」という4段階に分け、家族全員が安心して新生活を始められるよう詳しく解説します。

目次
家族全員の生活と気持ちの準備を整える
引越しが物理的に大変なのはもちろんですが、「生活の変化」「環境の変化」「感情の揺れ」に対しても、家族全員が事前に心の準備をすることが、引越しをスムーズに乗り越えるカギになります。
ここでは、家族・特に子どもの気持ちと日常を乱さずに引越しを進めるための具体的なポイントを解説します。
【1】家族会議で「引越しの目的と段取り」を共有
■ 目的を全員にわかりやすく説明
- 子どもにも年齢に応じて説明する(例:「新しい幼稚園に行くんだよ」「パパの会社が遠くなったからおうちを変えるよ」など)。
- 説明はできるだけ前向きな表現で(「もっと楽しい場所があるよ」「新しいお友達ができるよ」)。
■ タイムラインをざっくり共有
- 「来週は荷物をまとめようね」「この日にトラックが来るよ」と、ざっくりした日程感覚を家族みんなで持つことが安心感につながる。
【2】子どもの気持ちを尊重し、参加させる
■ 子どもが「置いていかれた感」を持たないように
- 荷物整理や箱詰めを一緒にやらせる(特に自分の持ち物は自分で選ばせる)。
- 「この箱は〇〇ちゃんの」など、引越しに“自分の役割”を感じさせる工夫が効果的。
■ 別れのケアも大切に
- 保育園・学校・習い事の友達や先生に、子ども自身からお別れの挨拶や手紙を書く機会をつくる。
- 写真やメッセージカードなどを残しておくと、子どもが気持ちを整理しやすい。
【3】普段の生活リズムをなるべく崩さない
■ 引越し準備期間も「生活の一貫性」を維持
- 荷造りで忙しくなっても、食事・お風呂・就寝などの時間は極力変えない。
- 子どもにとっては「毎日のルーティン=安心材料」。
■ 引越し前後の“遊び”を確保
- 荷物が減って遊びにくくなる時期でも、最低限のおもちゃやお気に入りアイテムは引越しギリギリまで残す。
- 外遊び・テレビ・絵本など、気分転換の手段を確保しておくとよい。
【4】住居選びの際は「家族目線の環境」を意識する
■ 生活動線と安全性を最優先に
- 子育て世帯なら、階段・ベランダの安全性、保育園や学校までの距離、交通量の少なさなどを重視。
- 通勤時間と家族の時間のバランスも大切(通勤が短縮されれば、家庭時間が増える可能性あり)。
■ 家族の意見を反映
- 内見に家族で行ける場合は子どもも同行し、「このお部屋どう思う?」と問いかけることで心理的な納得感が高まる。
【5】大人側も「精神的ゆとり」を持つ工夫を
■ 夫婦間のすり合わせを早めに
- 誰が何を担当するかを明確化(引越し業者の手配、書類整理、荷造り、子どものケアなど)。
- すべてを完璧にやろうとせず、「8割でOK」の意識を持つことも重要。
■ 不安や焦りを外に出す場を持つ
- SNSや日記に吐き出す/ママ友・パパ友・実家などに相談するなど、孤立せず誰かと共有することで精神的な余裕を保ちやすくなる。
引越しは「心の準備」と「段取り」で決まる
家族・子連れの引越しでは、段取りや手続きの前に“気持ちの整理と共有”が必要不可欠です。
とくに子どもにとっては「環境の変化」が大きなストレスになるため、心理的に納得できるプロセスをつくることが、新しい生活へのスムーズな移行につながります。

安全とストレスの最小化がポイント
家族・特に子連れでの引越し当日は、大量の荷物、出入りする業者、片付かない部屋の中を家族が動き回るという、非常に慌ただしい状況になります。
このような環境で事故やストレスを防ぐには、「安全の確保」と「ストレスを減らす工夫」が不可欠です。以下に、引越し当日のポイントを項目別に詳しく解説します。
【1】子どもの安全確保が最優先
■ 子どもを預けるのがベスト
- 引越し作業中は物の搬入・搬出で危険が多いため、親族・知人・一時保育・ベビーシッターなどに預けるのが理想。
- 特に0〜6歳(未就学児)の場合は、業者との作業が重なると非常に危険。
■ 自宅内で過ごす場合の工夫
- 一部屋を“安全エリア”として確保し、絵本・動画・おもちゃ・おやつなどを準備。
- 危険なもの(工具、刃物、掃除用品など)は完全に取り除き、子どもが勝手に出ないようにドアをロック。
【2】荷物の配置・荷解きの優先順位を決めておく
■ 「すぐ使うもの」ボックスを準備
- 子ども用と大人用で最低限必要なものを1箱にまとめておく(開封優先ボックス)。
- 子ども用:おむつ・着替え・哺乳瓶・お気に入りのおもちゃ・おやつ・保険証など
- 大人用:充電器・薬・ハサミ・タオル・現金・掃除用具など
■ 段ボールに中身と場所を記載
- 「キッチン①/調理器具」「子ども部屋②/おもちゃ」など、“誰が・どこに”片付けるか一目で分かるようにしておくと、荷解きもスムーズでストレス軽減。
【3】引越し業者とのスムーズな連携
■ 引越し業者に伝えるべきポイント
- 小さな子どもがいること、静かに作業してもらいたい時間帯(昼寝など)があること。
- 大型家具・精密機器など、特に慎重な扱いが必要な荷物の情報。
■ 当日の流れを事前に家族でシェア
- 「〇〇は業者が運ぶ」「これはママが自分で持つ」など、分担を明確にしておくと混乱が減る。
【4】引越し当日のストレスを最小限に抑える工夫
■ 食事は前日または早朝に準備 or 外部に頼る
- 調理道具や食器が使えないケースが多いため、前日に作り置きするか、弁当・デリバリーを活用。
- 子ども用のおやつや飲み物も個別に小袋で分けておくと便利。
■ 荷解きは「全部やらない」でOK
- 引越し当日にすべて終わらせようとせず、「3日暮らせるスペースがあればOK」の気持ちで。
- 優先度の高い場所から(寝室・トイレ・風呂・キッチン)徐々に進める。
【5】ストレスサインとその対処法(特に子ども)
■ よくあるストレスサイン
- 落ち着きがない、泣きやすい、抱っこをせがむ、体調を崩す、寝付きが悪くなる、急な赤ちゃん返り
■ 対処法
- 「いつもと違っても当然」というスタンスで叱らず、受け止める対応が基本
- 作業の合間に抱っこしたり、名前を呼んだり、「一緒にやろう」と声かけするだけでも安心感を与える
「引越し当日は“完璧”より“安心と無事”を優先する」
子どもや家族全員にとって、引越し当日は非日常のストレスフルな1日です。そのため、「完璧にやり切る」よりも「事故を防ぎ、安心して乗り越える」ことを最優先にしましょう。
段取り・役割分担・事前準備をしっかりしておくことで、バタバタする当日でも落ち着いて対応できます。

新生活の早期安定を意識
引越しを終えた直後は、環境の変化・荷物の混乱・手続きの多さなどから、心身ともに落ち着かない状況に陥りがちです。
特に子どもは環境の変化に敏感で、不安やストレスを抱えやすいため、引越し後の数日〜1週間が非常に重要です。
ここでは、新しい環境で家族が一日も早く「普通の生活」に戻るためのポイントを詳しく解説します。
【1】“3日暮らせる環境”を最初に整える
■ 最優先で設置すべき生活インフラ
| 分野 | 優先順位の高い準備項目 |
|---|---|
| 睡眠 | ベッド or 布団、カーテン(外からの視線・日差し防止) |
| 衛生 | トイレットペーパー、石けん、タオル、シャンプー、歯磨きセット |
| 食事 | 簡単な調理器具(電子レンジ、鍋など)、食器類、インスタント食品 |
| 子ども用 | おむつ・おしりふき・ミルク・哺乳瓶・お気に入りのおもちゃ・絵本など |
※「開封優先ボックス」にこれらをまとめておくと、探す手間が省けます。
【2】子どもに“日常感”を取り戻させる工夫
■ 子どものスペースは最優先で整備
- 遊びスペースや学習机、いつも使っていた布団・おもちゃなどを、引越し初日〜2日目までに設置。
- 「この部屋が〇〇ちゃんの場所だよ」と説明して、新しい生活への安心感を与える。
■ お気に入りアイテムをすぐ使えるようにする
- 絵本・ぬいぐるみ・おしゃぶりなど、子どもが落ち着く“安心アイテム”はすぐ出せる状態に。
- 同じ布団カバーやカーテンを使うなど、視覚的な“変わらなさ”も有効。
【3】生活リズムの早期確立
■ 食事・就寝・登園時間を引越し前とできるだけ揃える
- 新しい環境でも、食事の時間・入浴・就寝・起床時間を以前のスケジュールに合わせることで、「いつも通り」が生まれる。
- 荷ほどきや掃除で忙しくても、食事は家族で一緒に食べる時間を確保すると、気持ちの安定につながる。
■ 子どもの登園・通学スケジュールを早めに作る
- 通園・通学が始まるまでの期間がある場合でも、「起きる時間」「外に出る時間」などをシミュレーションしておくとスムーズ。
- 引越し後すぐ登校・登園する場合は、前日までに持ち物やルートを確認・練習しておく。
【4】新居周辺を“ホーム”と感じさせる工夫
■ 家族で地域散歩・買い物・公園へ
- 「あそこのお店でパン買おう」「この道を通って幼稚園に行くよ」など、新しい生活動線を体感的に覚えさせる。
- 公園や図書館など、子どもが楽しめる場所を早めに見つけて連れていくと、地域に対する安心感が増す。
■ ご近所との挨拶も大事な安心材料
- 両隣と上下階への簡単な挨拶で、「見知らぬ土地」から「知っている人がいる場所」へと印象が変わる。
【5】家族のメンタルケアと無理しない姿勢
■ 「全部片付けようとしない」「頑張りすぎない」が原則
- 荷ほどき・掃除・各種手続きは一気にやろうとせず、家族の心身の安定を優先。
- 子どもが不安定になったら、荷ほどきを止めてでも「一緒に遊ぶ」「抱っこする」などの対応を優先する柔軟さが大切。
■ 親自身の“安心ポイント”も早めに確保
- 最寄りの病院、ATM、スーパー、ドラッグストアなどをチェックしておくと、緊急時にも安心感がある。
- ストレスが溜まりそうなときは、一人の時間を確保することも大事な自衛手段。
新生活の“早期安定”は、「暮らしの土台」+「心の安心」から
引越し直後の混乱を抑えるには、“3日間生活できる環境”と“いつも通り”をできるだけ早く取り戻すことが重要です。
特に子どもにとっては、日常のリズムや親の安心感がそのまま反映されます。焦らず、段階的に整えることが家族全体の安定につながります。

子どもの変化に寄り添う
引越しという大きなライフイベントは、子どもにとっては“世界がガラリと変わる”ほどの大事件です。
親にとっては物理的な作業中心でも、子どもにとっては、友達・保育園・遊び場所・生活リズムなど、すべてが変わる不安要素になります。そのため、小さな変化に敏感に気づき、寄り添う姿勢がとても重要です。
【1】引越し後に見られやすい子どもの変化とは?
■ 典型的な“環境ストレス反応”
| 行動変化 | よくある反応例 |
|---|---|
| 感情面 | 不安・泣きやすい・怒りっぽい・機嫌が悪くなる |
| 行動面 | 赤ちゃん返り(夜泣き・甘え・おねしょ)/一人で寝たがらない |
| 身体面 | 食欲不振・便秘・下痢・頭痛・腹痛などの身体症状 |
| 社交面 | 新しい園や学校での無口・緊張・登園・登校の拒否感 |
※年齢が低いほど、言葉ではなく行動や体の変化に出やすい。
【2】親ができる「変化への寄り添い方」
■ 否定せず、気持ちを言葉にしてあげる
- 「新しいところ、ちょっとドキドキしてるんだよね」
- 「〇〇ちゃん、頑張ってるね。パパもママも引越ししてちょっと疲れちゃったよ」 → 気持ちを代弁してあげることで、子どもは“わかってもらえた”と感じられます。
■ 無理に新しい環境に慣れさせようとしない
- 「早く友達つくってきなさい」よりも、「今日はどんな人がいた?」という受け身的・共感的な接し方が効果的。
■ 家での安心感をしっかり提供
- お気に入りの毛布・ぬいぐるみ・絵本など、“変わらない日常の象徴”をそばに置いておく。
- 家では「よく知っている安心できる空間」を確保し、「帰る場所がある」と感じさせる。
【3】生活の“いつも通り”を重視する
■ 引越し後の“生活リズム再構築”は最優先
- 就寝・起床・食事・お風呂の時間を、引越し前のタイムスケジュールにできるだけ近づける。
- 通園・通学前に何度かルートを一緒に歩いたり、先生や園の雰囲気を伝えるだけでも子どもは安心する。
【4】園・学校と積極的に連携する
■ 担任の先生・保育士に状況を伝える
- 「引越しして間もないので、少し不安定かもしれません」と伝えておくだけで、保育・教育現場でのケアがスムーズになります。
- 慣れるまでは、登園・登校後も10〜15分付き添う・先生に引き渡すなども効果的。
【5】変化が長引く・強く出るときは専門家に相談も視野に
■ 以下のようなサインが長期間続く場合は相談を
- 登校・登園拒否が2週間以上続く
- 睡眠障害・情緒不安・身体症状が継続する
- 家でも園でも常に無気力・無反応・過度に暴れるなどの状態が続く
→ 自治体の子育て支援センター、発達支援センター、スクールカウンセラーなどの公的機関が無料相談窓口として利用できます。
【6】親自身の不安も「子どもに伝わる」と意識する
- 引越し後の疲労・新生活への不安・仕事の調整など、親もストレスがかかる時期。
- 完璧にやろうとせず、「大丈夫、大人も疲れるから一緒に少しずつ慣れていこうね」と共感型で伝えることが子どもに安心感を与えます。
「寄り添い=無理に慣れさせない、安心できる土台を一緒に作ること」
子どもにとっての安心は、「変わってしまったこと」ではなく、「変わらずそばにいてくれる人」があるかどうかで決まります。
急がせず、否定せず、小さな安心を積み重ねていくことが、子ども自身の適応力と心の安定を育ててくれます。

家族引越しの効率UPポイントまとめ
家族での引越しは、荷物の量・作業人数・手続きの多さなどが単身引越しと比べて圧倒的に多くなります。
しかし、工夫と段取り次第で作業時間や負担を大幅に削減することができます。ここでは、引越しの各フェーズにおいて活用できる「効率アップの実践的なポイント」を詳しくご紹介します。
【1】家族全員の「役割分担」を明確にする
■ 大人同士で事前にすり合わせ
- 引越し前から「誰が何をやるか」を明確にしておくことで、無駄な動き・指示待ちの時間を防止。
- 例:パパ=業者手配・大型家電の養生
ママ=子どもの持ち物整理・行政手続き
中学生の子ども=おもちゃ/本の箱詰め担当 など
- 例:パパ=業者手配・大型家電の養生
■ 子どもにも「できること」を任せる
- 「自分の文房具はこの箱に入れてね」「ラベルを貼ってね」など、小さなタスクでも主体的に関われるように工夫。
【2】荷造りは“段階式”+“ゾーン別”で効率的に
■ 使う頻度別に箱詰め順を明確に
| 使用頻度 | 荷造り時期 | 例 |
|---|---|---|
| 使わない物(季節外の服など) | 2~3週間前 | 冬物・アルバム・飾り物 |
| 週1回程度の物 | 1週間前 | 調理器具、書類、ゲーム機 |
| 毎日使う物 | 前日~当日朝 | 洗面用具、常備薬、子どもの寝具 |
■ 部屋ごとにまとめておくと効率的
- 「寝室」「キッチン」「子ども部屋」などでゾーン分けし、箱にも部屋名を明記。
- → 引越し先での荷解きも“部屋ごと”に効率よく進められる。
【3】引越し業者は“家族向けプラン”を活用する
■ ファミリー向け業者の特徴
- 訪問見積もりあり/梱包・開梱サービスつき/大型家具の設置対応/養生・保険完備
- 子育て世帯向けの割引や時間指定などがある業者も
■ 見積もりは必ず「相見積もり(3社以上)」を
- 同じ条件でも数万円の差が出ることがあるので、複数社から見積もりをとるのが鉄則。
- 土日祝・月末・春の繁忙期は料金が高騰しやすいため、平日・中旬の引越しが狙い目。
【4】手間のかかる手続きは“まとめて”&“事前処理”が基本
■ 役所関連は1日で終わらせるように段取り
- 転出届/転入届/児童手当/医療証/マイナンバー/印鑑登録など、リスト化して一気に処理。
- 同時に保育園や学校の転入手続きも行えば、何度も役所に行かずに済む。
■ 電気・ガス・水道・ネットは一括申請サービスを利用
- 「引越し侍」「ライフライン一括手続き」などの無料サービスを使えば、電話1本で手続き完了&漏れ防止。
【5】生活リズムと食事は「割り切って」乗り切る
■ 食事は“つくる”より“備える・買う”
- 冷凍・レトルト・宅配弁当・冷蔵庫の作り置きなどを事前に準備。
- 引越し前後の2~3日は「作らなくて当たり前」にしておくことで、ストレス軽減+子どもの不機嫌防止。
■ 睡眠とお風呂は最優先で準備
- 子ども用布団やベッド、パジャマ・タオル類は早めに取り出しておく。
- 「寝る環境だけは初日に整える」ことを目標に、荷ほどきの順番を調整。
【6】近隣への挨拶で“トラブル防止”と“安心感”
■ 挨拶の範囲と方法
| 対象 | 挨拶する理由 |
|---|---|
| 両隣・上下階 | 騒音や出入りがあるため |
| 管理人・大家 | 何かトラブルがあったときの印象が大事 |
- 簡単な手土産(500円程度のタオル・お茶など)を添えて挨拶すると丁寧。
- 小さい子どもがいることを伝えておくと、生活音に対する理解が得られやすい。
家族引越しの効率UPは「分担×段取り×割り切り」がカギ
家族の引越しは、「すべてを完璧にやる」のではなく、「やるべきことに集中し、手を抜くべきは抜く」ことが成功のコツです。
子どもとの時間、仕事との両立、生活リズムの維持など、家族ごとの優先順位を明確にし、準備→実行→立て直しまでを段取り化することで、引越しは驚くほどスムーズになります。

家族・子連れの引越しは「心の移動」も意識する
家族や子どもと一緒にする引越しは、単に“住む場所が変わる”だけではありません。
特に子どもにとっては「人間関係」「習慣」「安心できる空間」すべてが一度に変わるため、心理的な負担が非常に大きくなります。
だからこそ、引越しは「心の移動」をどう支えるかが成功のカギになります。
【1】「心の移動」とは何か?
■ 単なる物理的な移動ではない
- 子どもにとっての「日常」とは、自宅・幼稚園や学校・近所の友達・通い慣れた道・見慣れた景色など、目に見えない“心の居場所”も含まれます。
- 引越しは、これらが一気に“ゼロリセット”される出来事です。
■ 心の移動=「新しい環境に心が追いつくプロセス」
- 子どもや家族が、「今までの場所を離れた」ことを実感し、「新しい場所に根を下ろす」までの心の移行期間が必要です。
【2】引越し前にできる“心の準備”
■ 子どもには前向きな言葉で説明を
- 年齢に応じて、「新しい家の楽しみ」「新しい公園」「新しい学校」など、未来への期待感を含めた説明が効果的。
- 同時に、「今の家・友達と離れるのは寂しいよね」と、ネガティブな感情も否定せず受け止めることが重要。
■ お別れをきちんとする機会をつくる
- 友達にお手紙を書く/先生にあいさつする/写真を残すなど、心の区切りを持たせることで、「終わりと始まり」がつながりやすくなります。
【3】引越し当日・直後の“心のフォロー”
■ 不安定な行動が出ても「受け止める姿勢」が大事
- 甘えや赤ちゃん返り、登校渋り、夜泣きなどはよくある反応。
- 「なんで泣くの?」「もうお兄ちゃんでしょ」と叱るのではなく、「そうだよね、不安だよね」と寄り添う声かけが心の回復を早めます。
■ “変わらない要素”を引越し後も継続する
- お気に入りの布団やぬいぐるみ、朝ごはんのメニューなど、「いつものもの」「いつものこと」をできる限り新居でも再現。
- 「ここでも、いつも通りの自分でいられる」という感覚が安心に繋がります。
【4】新しい場所で「心の居場所」をつくっていく
■ 子どもが安心できる環境を早めに整備
- 自分だけの机や本棚、遊び場所を用意して「ここがあなたの場所だよ」と伝える。
- 公園、図書館、スーパーなどに一緒に出かけて地域の“日常風景”を体験させる。
■ 「家族の変わらない時間」が心の拠り所になる
- 毎晩一緒に夕飯を食べる・絵本を読む・一緒に散歩するなど、家族だけの変わらないリズムが“安心の軸”になります。
【5】親自身も「心の変化」に敏感になる
■ 子どもだけでなく、親も“変化にさらされている”
- 引越し作業、生活基盤の再構築、仕事の両立など、親も無意識にストレスを受けています。
- 親が無理をし過ぎると、イライラや焦りが子どもにも伝わってしまうため、自分自身の気持ちも労わる意識が大切です。
「心の移動」を整えることが、家族全体の“新しい日常”を支える
家族の引越しは、「運ぶ・片付ける」だけでなく、気持ちに折り合いをつけ、前を向くプロセスをサポートすることが本質です。
「気持ちが置き去りにされないように」「心にも引越し先があるように」そうした意識で行動すれば、新しい暮らしはぐっと安心感のあるものになります。

異なる事情・ニーズ【関連ページ】
- 一般的な引越しと異なる事情・ニーズ
- 単身赴任・一人暮らし向け引越しガイド
- 家族・子連れの引越し完全マニュアル
- カップル・同棲開始引越しガイド
- 高齢者・介護を伴う引越し
- 離婚・別居に伴う引越し
- 転職・異動を伴う引越し
- 単身引越しの賢い方法
- 長距離引越しを賢く行う方法
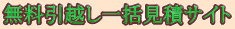
・ズバット引越し比較 ![]() 当サイトNo1利用率
当サイトNo1利用率
大手から中小まで全国220社以上の業者と提携しており最短1分で一番安い業者が探せる優良一括見積サイト。
・引越し侍![]()
CMでおなじみの引越し一括見積りサイトです。全国352社の業者と提携しており5,068万件という紹介をしています。
・引越し価格ガイド![]()
利用者の95.2%がまた利用したいという一括見積サイト
・引越しラクっとNAVI![]()
ビデオ通話によるオンライン見積もりも。専用のサポートセンターが1度ヒアリングをすることで、引越し会社と話すことなく見積りが出てきます。

